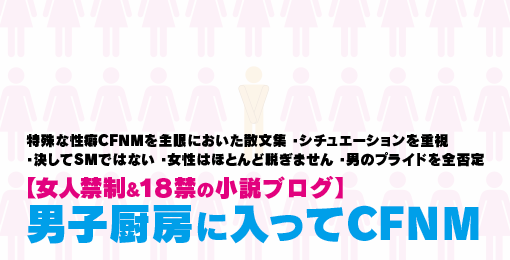「さぁ、自分で握ってみて」
姫乃はすっかりお姉さんのように僕を上から見下ろす感じになった。童顔で背が低いのに不思議なものだ。胸だってない癖に加虐的な瞳は情けない僕をコントロールしてくる。
「ぅぅ…」
命令されるまま、右手でしっかと自らの肉棒を握り込んだ。姫乃に両足を広げられたままなので恥ずかしい部分が余すところなく公開中である。
「猛雄くんは~、女子にたくさん恥ずかしいとこ見られちゃってるのに興奮してるんだね」
微笑みのような嘲りのような姫乃の表情。僕は口を開けたまま見惚れていた。
「変態さんなんだ?」
「いやぁ、違うって… ハァハァ…。仕方がねーから言う通りにしてやってるだけで……」
「でも先っちょから透明なお汁が出てきちゃってるよ? これは何なんですかー?」
カーテンに仕切られた空間で小声ながらも問い詰める口調の姫乃。
さらにがばっと足を開脚させてお尻を上げられる。
「ぁあぅ…」
お尻の穴までばっちり晒してしまう角度だ。
「やだぁ、ちょっと臭ぁい。ちゃんと拭いたの~」
「ぅぅへぇ…」
さすがに恥ずかしくなる。拭き残しなんてないはずだ…。姫乃は嘘を言っている!
「シワシワ~」
「お、下ろして……」
全裸の上にお知りの穴まで見られて、おちんちんははち切れんばかりに膨張していた。苦しくて切ない。どうすればいいんだっ。
おまじないとやらを早くして欲しい。僕を救済してくれっ。
「うふふっ。猛雄くん、お手々が動いてるー」
「はぇっ」
勝手に右手が動いていた。もぞもぞと変な感じ。こそばゆい。なんだろう。これはものすごく恥ずかしい行為だ。両足を閉じようと思った。だが姫乃にこじ開けられたまま動かせない。
震えてきた。
怖い。
天空から見守る女神のような姫乃の微笑み。
「あぐ…」
僕は左手で口を抑えた。
おちんちんを握っていると快楽にも似た刺激が全身を駆け巡る。パッと右手を離して、代わりに勃起おちんちんを見られないように覆う。
ここから先は未知の世界だ。僕には踏み込めない。
まだ見ぬ大人の世界に恐怖して僕は涙を流していた。
「やめちゃうの?」姫乃は前進してきた。ちんぐり返しされてしまう。「なんで隠すのかなー。もっと見せてよ。皮がたくさん余ってる右曲がりの無毛おちんちんをさ~」
完全にいじめっ子の目をした姫乃。頬を上気させ彼女も興奮した様子だ。何かに取り憑かれたみたいに僕に覆いかぶさる。
「ぁへぇ」
自分の足の裏が視界に入る。ちんぐり返っておちんちんの先っちょもこちらを向いていた。僕の閉じた蕾がわずかに開き始めていた。透明の液体がだくだくと垂れだす。
「うふふ」
にんまりとした姫乃は両手をベッドに着いた。完全に僕の股の間に身体を入れ込むかたちで、僕が足を閉じるのを防いでいる。僕の右手を退かし、そして右手をおちんちんに伸ばしてきた。
「ぁふぅ…」
ヨダレがベッドに垂れた。
「あったかーい。硬いね~。へぇ~……。ぁ、触っていいよね?」
事後承諾かよっ。
僕は漏れそうになる声を両手で塞いでいた。
首を振ってもうコレ以上はやめて欲しいと懇願する。だが姫乃は僕の意思表示などお構いなしにニギニギしてくる。
「あはは、おもしろいね。べちょべちょだー。いやらしー。汚ーい」
姫乃はもう片方の手も使っておちんちんを遠慮なく触る。
「おしっこの出る穴はどうなってるのかな」
姫乃は好奇心だけで突き進み、僕はもう地中深くにまで押し込められていた。
余った皮を剥き始める姫乃。左手で根本を固定し、剥きぃ剥きぃとバナナの皮を剥くように右手の指先を使う。未使用の亀頭が露出する。初めて世界に顔を出した亀頭は生まれたての仔鹿のように震えていた。
「真っピンクだー。かっわいいー」
もはや僕は彼女のおもちゃと化していた。
僕は足をジタバタとさせて、逃げたくて仕方がない。だが姫乃は支配的だ。マウンティングされて僕に自由はない。
いつもと変わらぬ普段着の姫乃の下で僕は亀頭やお尻の穴まで丸出しのすっぽんぽんである。絨毯爆撃の中を竹槍で立ち向かっていくようなものじゃないか。この格差に僕は男性としての自信のようなものを失っていった。
姫乃は僕を支配下に治めたというわけだ。
「おまじないしてあげるね。いいこいいこー」
子どもの頭を撫でるように亀頭を小指の腹で撫でてきた。全身に電撃を与えられたように僕は跳ねる。
「ほんとは自分でやらないとダメなんだからねー。今日は特別に私がやってあげるから。いいこいいこー」
透明の汁のせいで、ぬめりが亀頭を襲う。僕は姫乃の小指一つでジタバタと動かされるのだ。日本男児が女子なんかにいいように扱われて情けない限りだ。
「ふごーっ!」
「いいこいいこー」
完全に舐められている。虚仮にされているのだ。悔しいけど手も足も出ないまま僕は白目を剥いていた。急激な尿意と共に意識が飛んでいく…。
どぴゅっっ!
ぴゅぴゅぴゅっ
ぴゅうっ
たくさんのどろっとしたものが僕の顔面に降り注いだのだった。