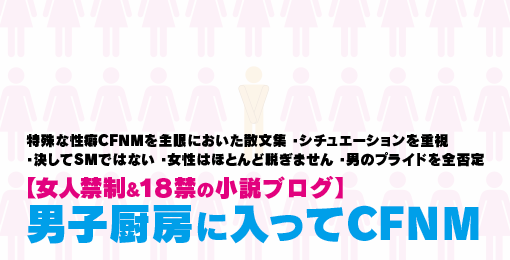ツイスターゲームは女子たちだけで大いに盛り上がった。
俺はと言うとダイニングのテーブルでグラスを片手にスナック菓子を口に入れているだけだ。味などしない。そして少しも楽しくない。当たり前だろう。女どもがキャッキャと楽しそうにしていても男にとっては苦痛の時間なのだ。
ましてや男子は俺一人だけ。女子のほうでも俺のことを腫れ物のように扱っているようだ。わざと話しかけないようにしている…。敵視すらしているみたいだし。俺だって好きで来たんじゃないのに。
帰ろうにも、中邑のお母さんが入り口付近のイスに陣取っているため、悪い気がして出ていけない。
「楽しんでる?」
静香さんが隣の席に座ってくる。「コーラでも飲む?」と紙コップを持ってきて注いだ。
「いつも麻里子と仲良くしてくれてありがとうね」
などとお姉さんは笑顔で接してくれた。
「一人じゃつまんないでしょ? こういうときは男も女も関係なく騒いだほうが楽しいんだから」
「はぁ…」
そう言われても男が女子なんかと遊ぶのは格好悪いと思う。男は男同士でサッカーとか野球をやるもんだ。女のママゴトに付き合うなんて他の男子にバレたら仲間に入れてもらえなくなる。
「一緒に遊んだら?」
「うぇ〜…」
俺は嫌そうに答えていた。
「みんなも男の子と遊ぶのを恥ずかしがってるだけなんだから。君から声をかけなきゃ。ほら、入れてって。言ってみたら?」
「そんなことできるわけねーしぃ〜…」
「じゃあ、お姉ちゃんと遊ぶ?」
「ぃ、いやぁ〜…」
段々と顔が熱くなってきた。少し歳上の女に優しくされるとどうしていいか解らない。ドギマギとしてしまった。そんなことをおくびにも出さないように俺はぶっきらぼうに「あいつらと遊んでも楽しくねーし」とか「女とは遊べんっ」などと答えていた。
「ほらいこっ」
静香さんは俺の言ったことを聞いていなかったのか手を引っ張ってリビングの中央に連れて行く。俺は仕方なく嫌々だが女の園へ降り立った。
「みんな。草凪くんも一緒に遊びたいって」
そして言ってもいないことを静香さんはみんなに告げるのだった。
「は? 遊びたい?」
笹木は口の端を少し捩じ上げた。いかにも小馬鹿にしたような感じだ。ムカつく顔をしているが、ツイスターゲームの途中で四つん這いになって苦しそうな顔をしているので、それで少しは溜飲が下がった。
「あんたからそんなこと言うなんて珍しいじゃん」
「い、言ってねーし!」
「でもまぁ入れてあげようよ。せっかく来たんだから」
中邑がソファの中央から慈悲深い言葉を告げる。普段と違って着飾った彼女はまるで王女様のように気品に満ち溢れていた。
「でもなー。プレゼントも持ってこないヤツがさー」
喜多野が振り向きざまに蔑んだ目をする。ツイスターゲームの途中で大股を開いて笹木に跨っていた。
「ふつー持ってくるよな」
がさつで有名な彼女らしく、誰もが思っていて口にしなかった俺の非礼を憚(はばか)りもなく責め立てた。
「あーアタシも思ったソレ。渡部の妹ちゃんでも色鉛筆セット持ってきたのに」
砂藤が続く。
「そうそう、常識がないんだよ。草凪は」
笹木が解ったような口調で後を継いで言い放った。
「もー…。それは別にいいんじゃない?」
中邑はこれ以上言ってやるなよといった感じで少し困った顔をする。
「男子だからしょーがないか」
渓口が床に寝っ転がったまま口を挟んだ。
「でもさー。こういうことはちゃんとしたほうがいいって」
砂藤はしかし譲らない。プレゼントも持ってこないようなやつを仲間に入れるべきではないと厳しい。全体的にはどちらかと言うとみんな同じ意見のようで、中邑もそれ以上は擁護できなくなってくる。
「くっ」
どうしても遊びたいなんて言ったつもりもないのに。俺がワガママを言っているみたいじゃないか。いつの間にか静香さんもダイニングに戻ってしまったようだし、俺も引き返そうと思った。
「何か芸したら?」
「あー、そういうんでもイイんじゃない?」
笹木と砂藤が頷きあった。
な、なんだと…。
「プレゼント代わりに皿回しとかして盛り上げなよ」と砂藤。
「歌とかダンスは?」と渓口。
「草凪にできるわけないでしょ」と中邑。
「腹芸ならどう? 誰でもできるし」と杁山。
「キモーい。イヤー」と渡部の妹。
女子どもは俺の意見も聞かずに勝手に盛り上がり始めた。
「何やってもらう?」
渓口などはキラキラした目で足をバタバタさせている。
「草凪100%やったら?」
笹木が被虐的な笑みを浮かべて俺を見る。
「な…」
「得意でしょ? あんた」
「ぇ…」
「裸芸とか前にやってたし」
「いや、アレは…」
芸じゃない。消したい過去の話をしないで欲しい。
「いいじゃんソレ」と渓口。
「ぷっ 草凪100%。おもしろそー」と山元。
「プレゼントがないんだからそれで許してあげるわ」と砂藤。
「やぁだー」と中邑。
「草凪得意の噂の裸芸ね。やってよ!」と柏城。
「手ぶらで来たんだからそれくらいやれやれっ」と笑う喜多野。
俺は口を挟めずにジリジリと下がる。
しかし笹木は確信犯的に俺を追い詰めてきた。
「一緒に遊びたいんでしょっ。あんた裸になるのに躊躇しないキャラなんだからいいじゃん」
「おぼんでアソコ隠すんだよね!」
渓口が身体を起こしておぼんを探しに行った。
ダイニングでゆったりと寛ぐ中邑のお母さんとお姉さんは子どもたちの暴走を「あらあら微笑ましいわね」みたいな様子で眺めているだけだ。おぼんを取りに行った渓口に「これでいいんじゃない?」と紙皿を渡す。
直径15センチくらいの小さいやつだ。
「やーれっ やーれっ」
女子たちは妙な盛り上がりで手拍子を始めた。渓口が戻ってきて紙皿を俺に渡す。笹木は俺の背を押してベランダの前に追いやる。
「いや… あ…」
全国のお茶の間にアソコさえ隠していれば裸で登場してもいいという市民権を得てしまったアノ裸芸。眉をひそめる親御さんも多い中、中邑のお母さんは寛容だった。お姉さんも笑顔で見守っている。中邑は眉根を寄せながらも苦笑いで止めはしない。
もはや誰も咎めない。
「やれコール」でオーディエンスが盛り上がり、ツイスターゲームは中断され、女子たちは期待の目で俺を注目する。
あの時の記憶が蘇ってきた。
堂々としていればいいのだ。恥ずかしいことなんてなにもない。
それに『100%』の芸は見せないことに重点が置かれるものだ。テレビに普通に出られる立派な芸である。確実に隠していればいいのだから修学旅行のときより気が楽というもの。
俺はやれる。
簡単だろう、あんなもん。
紙皿を床に置いて、Tシャツに手をかける。