好奇の目を向けた女子たちが健次郎の周りに集まっていた。ピアノを取り囲んでいる。彼女たちは一様に高揚した表情を健次郎に向けていた。
ピアノの演奏者は自分だった。
服も何も身にまとっていない、産まれたままの姿である。
靴下もパンツも履いていなかった。恥ずかしいが何もかも晒して、ピアノの演奏をしなければいけないらしい。
高揚しているのは女子たちばかりではない。健次郎自身も顔を赤くしていて、心臓も高鳴っている。おちんちんも血管を浮き立てて見事に勃起させていた。裸のままイスに腰掛けている。股の間から元気よく上を向いたおちんちんがびくびくと反応していた。
誰も声を発しないこの空間で、女子たちが息を呑む音、自分の心臓の音が響き渡る。その間をぬってヴィ〜…っと何かの振動音が部屋中にこだましていた。
健次郎は息をのんで鍵盤に指をあてがう。彼は裸で、おちんちんを屹立させたまんま、不公平にも服を着た女子たちに囲まれて演奏をしなければいけないこの状況に、屈辱的で悔しい筈なのに、言いようのない幸福感を味わっているようだった。
今夜は最高の演奏ができそうだ。
健次郎は少し早く来過ぎたなと思いながらソファに腰を沈める。
「はぁ、かったりぃぜ…」
肩を揉みながら、足を組んで机の上に投げ出して置いた。ついでにカバンもテーブルに放る。続いて大きなあくびをし、時計を見やった。レッスンが始まるまで、まだ15分ほどある。
先生と生徒のマンツーマンで行われるレッスンだから、健次郎の前にレッスンを受けている生徒がまだ教室にいるようだった。教室の中から軽やかな演奏が聴こえてくる。
素直できれいな音色だ。演奏者の性格が伺えるというものだ。
だが、今の健次郎にとって真剣に演奏を聴いて耳を養うなどということは意味のないことだった。どんな演奏を聴いたって心に響いてこないのだ。
やがて眠くなって、5分程度だったらうとうとと眠っても大丈夫だろうとまぶたを閉じる。
だが、後にこんなところで寝なければ良かったと後悔することになる。
「あら、いつもは遅刻してくるのに珍しィね」
ミレーヌと眞美がレッスンを終えて教室から出てくる。ミレーヌは控え室にぐでんと眠りこける健次郎を目にして、優しく微笑んだ。
「あら、まァ、この子ったらっ。ふふ…」
「先生…ちょっと…この子…」
眞美はハッと息を呑む。
手足を投げ出して、態度の悪い男の子がいるというだけで不愉快だったが、それにも増して許せないものを見てしまったのだ。
「はしたないわっ…」
眞美は健次郎の股間の辺りに膨らみがあるのを認める。
「勃起してるんだわ…コイツ…」
「起きなさい、ケンジロー」
ミレーヌに揺さぶられて起こされて、健次郎は寝ぼけ眼で目を擦りながら起き上がった。
「なんだよ、もう飯?」
「あなた今とても良いコンディションのようね。いいわ。すぐにでもレッスンを始めましょう。さァ早く早く」
「え? レッス…。あぁ俺…」
健次郎は周りを見回して、今の自分の状況を理解した。前の生徒である眞美が侮蔑するような眼差しで健次郎を見ていた。健次郎は自分の股間が熱くなっているのに気付いて、ハッとカバンをすばやく取って股間にあてがう。
「そうだ、ケンジロー。あなたまだ逢ったことなかったわね。この娘は時村眞美さんよ。眞美さん、こちらは有名人だからご存知かしら? 数年前にケンジロー林田の名前でクラシック界に現れた新星よ。あなたたちは歳も近いし、仲良くしなさいね」
「ちょ…、せ、先生よぉ。新星とかやめろって」
健次郎はちらりと紹介された眞美を見る。制服の白いブラウスがまぶしい。しっとりと艶やかな黒髪とのコントラストが目を引いた。意思の強そうな目、ものをハッキリ言いそうな口の形。裕福な家庭で育ったのだろう。小さく高級そうな腕時計、髪留め、頬の赤らみ、立ち居振る舞い、どれをとっても庶民にはないオーラを放っていた。
制服を見れば、自分と同じ学校の生徒のようだとわかるが、同じ学年では見かけたことがない。
「また、お茶会を開くからねェ。ケンジローもいらっしゃいな」
「わかったわかった」
健次郎はミレーヌの会話から逃げるように、挨拶もせずおちんちんを勃起させたまま教室の中へそそくさと移動していく。
眞美は勃起したまま教室に入っていく健次郎を見て、眉根を寄せて口元を歪めた。
「…失礼にも程があるわ…」
「さァ、鍵盤を思う存分叩きなさい」
「いや、先生…。ちょっと、お…落ち着くまで待ってくれよ」
「何を言ってるの!? 今のコンディションであることが重要なのよ」
「はぁ?」
健次郎はイスに座ってはみたものの、少し前屈みになって顔を赤らめ演奏を始めようとしなかった。
「先生は知っているのよォ? あなたが磨けばカンブリア爆発する才能をね」
ミレーヌはヨーロッパでは有名なピアニストだった。若くして様々な賞を総なめにしてきた実力者である。未だに腕や美貌は衰えていなかった。さらさらの金髪や流暢な日本語、細くくびれた腰に大きなバスト。長いまつげ、鼻が高く、ぷっくりとした唇が人目を惹く。
「なんだよカブ爆発? 暴落のことか?」
健次郎が前屈みのまま渋っているとミレーヌは健次郎の制服のシャツを掴んでたくし上げた。すると黒いズボンの股間辺りに膨らみがあるのは一目瞭然。健次郎は慌ててミレーヌの手を振り払った。
「なにすんだよっ…」
「あなたは小学生の頃、“鍵盤の上の妖精”と呼ばれていたわ。世界の舞台でだって戦える才能があった。でも今は…いろいろ考え過ぎたのかもね。私は長いスランプだと思っていたの。でもそれは違った。あなたにはコンディションの調整が必要だったのね。今のコンディションなら昔よりも鍵盤の上でもっと美しく踊ることができるわ」
「何言ってるかわかんねぇよ」
「さァ弾いてみなさい」
「…」
健次郎は言われるままにピアノを弾いていった。確かに高揚してくるものがあった。何も考えずにあの頃を取り戻したかのような感覚。
ミレーヌは健次郎の背後に回って、つんっとおちんちんを指で突ついた。
「ぁ…」
「そのまま、やめないで続けて」
「ぉお…お」
健次郎は楽譜も見ないで、遠い昔に覚えている感覚だけで鍵盤を叩いた。ミレーヌがその細くしなやかな指で健次郎のお尻を撫でる。
「ぇ? …え?」
「続けなさい」
健次郎のおちんちんがむくむくと大きくなり、ズボンを突き破らんと上を向いた。ミレーヌが肩に優しく左手を添える。ミレーヌに促されるまま目をつぶって健次郎の指が鍵盤の上で踊った。
「…はぁ…ぁ」
顔を赤らめて背筋を伸ばした健次郎。ミレーヌはさらに健次郎のおちんちんをさすってやる。おちんちんがさらに上向きになってびくびくと暴れていた。
眞美は控え室に残ったまま健次郎の演奏を聴いていた。姿勢を正して、目をつぶり、ソファに腰掛けている。
日本に戻ってきて一年。このような才能があったとは…。眞美は膝の上の両手をきゅっと握りしめた。
正直に言えば自分の才能を凌駕しているといっていい。
眞美は小さい頃からピアノを習い、たくさんの大人に誉められてきた。日本での賞より外国での賞が多い。同世代の女子より頭一つ抜けたと自他ともに認める才能と言って良い。
しかし、天才たちの中に紛れれば自分だって凡庸であることを知っている。多くは上の世代に敵が多いのであるが、意外にも同世代、いや下の世代の中にも敵がいたのだ。
眞美は唇をかむ。
「なんでよ…」
それでも聴き惚れて、時間が経つのを忘れていた。
次のレッスンの生徒である優里亜が控え室に入ってきた。
「あ、こんにちは。橘さん、どうぞお掛けになって」
「こんにちは、眞美さん。珍しいですね。こちらでお会いするなんて」
5人分は裕に座れるソファに、言われるまでもなく優里亜は自由に腰掛ける。橘 優里亜は一つ年下の後輩で眞美をとても慕っている。整った顔立ちであるが控えめな印象を受ける女子だ。三つ編みと銀縁フレームのメガネがそう思わせるのかもしれない。
「少し、気になりましてね。この演奏を聴いていたのですが…、私、もう帰りますわ」
「そうですか。…確かに荒々しい音色もありますけど、なんて言うのかしら、情熱的でもありますよね」
「…そうですね」
「あ、お疲れさまでした」
控えめな笑顔で見送る優里亜だった。
やっと勃起が治まった。一時間近く勃起していたことになる。
「やっと解放されたのはいいけど…、やべ…。パンツちょっと汚しちまった…」
健次郎が股間を気にしながら玄関を出ると、外は夕闇が深くなり始めていた。先生の家の塀のところに誰か人がいる。
こちらが気付くとその少女はゆっくりと近づいてきた。
「待っていましたよ。あなたのこと少し訊かせてもらいたいと思っていましたの」
「…はぁ?」
健次郎はちょっと後ずさりした。この少女は眞美といったか、さきほどの控え室で勃起していたおちんちんをズボン越しに見られているのだ。気恥ずかしくて顔を合わせられなかった。
「少し一緒に歩きましょう?」
「え? ぁあ…」
言われるまま、健次郎は眞美と距離をとって歩き始めた。女子と一緒に肩を並べて帰るなんて初めてだ。健次郎はなるべく眞美の顔を見ないようにそっぽを向いて歩いた。
「控え室で少し聴かせていただいたわ。あなたなかなかの腕ね」
「はぁ」
「ぜひ、皆さんにも聴かせてあげたいと思ったのですよ」
「ぇー、…はぁ」
「私の家で小さなサロンを開きますの。定期的にやっていましてね。そちらへいらっしゃらない?」
「い、いや…え?」
「何人かで集まってお茶をしながらピアノの演奏をするだけですから」
「はぁ」
「メールのアドレスか電話番号を教えてください」
「んえ?」
健次郎は思わず変な声を上げてしまった。女子にモテたことなんてないのにいきなり電話番号を訊かれるなんて…。
「ま、まあ…」
そうして、健次郎は深く考えずにメールのアドレスを教えた。舞い上がっていたのかもしれない。
「それでは、また連絡致しますね」
眞美は表情をほころばせて、小さく手を振り、小走りに今まで来た道を戻っていった。わざわざ帰り道が違うのに…付き合ってくれたのか。初めはつんけんしてそうだなと思ったが割かし可愛いところもあるようだ。
黒髪を揺らしながら駆ける眞美の後ろ姿を見蕩れていた。
シャンプーの良い香りがかすかに残っている。
ぴくっ
おちんちんが少し反応しかけていた。
「これは俺たち、もう…付き合ってるってことだよな?」
健次郎はにやけながら帰路につくのだった。
レッスンの後で(1)
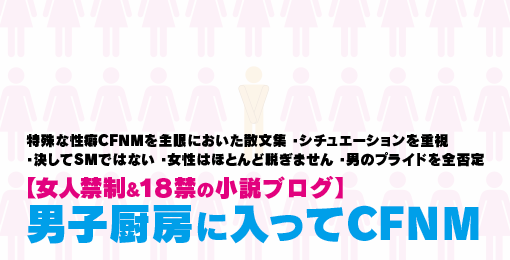 ・ピアノレッスンの後で ブログ版
・ピアノレッスンの後で ブログ版
